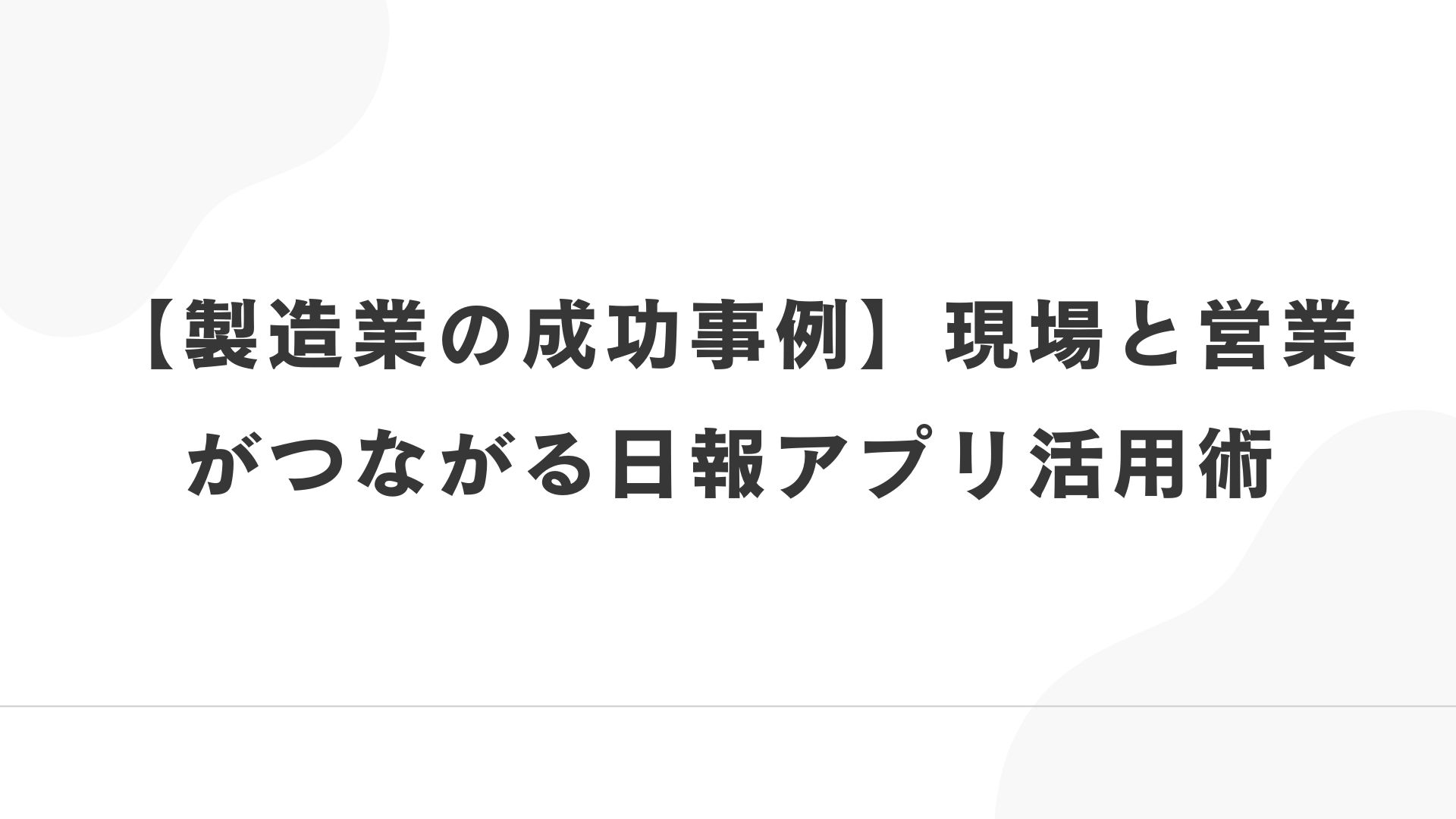
「現場と営業の情報が分断されている」「改善提案が埋もれてしまう」そんな製造業の課題を解消する仕組みが、日報アプリです。
報告や提案がリアルタイムで共有され、現場の声がそのまま改善行動につながる。日報アプリは、製造業の改善が回り続ける仕組みをつくっています。
印刷・製本業の株式会社MOTOMURAでは、アプリ導入によって現場と営業が同じ情報を常に共有しながら改善を進める体制を実現しました。
本記事では、株式会社MOTOMURAがどのように日報アプリを活用し、製造業の現場に改善が回る仕組みを築いたのかを紹介します。
導入の背景:チャットツールでは共有しきれなかった現場の声
株式会社MOTOMURAでは、日々の報告をチャットツールで共有していました。しかし、チャットは即時性が高い反面、重要な情報が流れやすく、あとから見返したり整理したりすることが難しいという課題がありました。
特に、「改善提案」や「お客様からの声」といった、会社全体で蓄積・活用すべき情報が埋もれてしまうことが問題でした。現場から上がった気づきや意見が、日々のメッセージに埋もれて次の改善につながらない。そうした状況を見直すために、同社は「日報という仕組みを再設計する」必要性を感じていました。
そこで着目したのが、日報アプリです。報告・提案・改善の流れをひとつのプラットフォーム上で管理でき、過去の投稿を簡単に検索・参照できるため、情報を「流す」から「蓄積し活かす」形へと変えられると考えました。
日報アプリの導入により、営業と現場の情報がひとつの場に集約。現場が生産記録を投稿し、営業が顧客フィードバックを共有することで、社内の情報がリアルタイムに循環する仕組みが整いました。

営業と現場がリアルタイムで情報共有
株式会社MOTOMURAでは、日報アプリを「全社員がつながる情報共有の場」として運用しています。営業・製造・管理の各部門が共通のグループに参加し、テンプレートを使って日々の報告や改善提案を投稿する仕組みです。
全社員に配布しているiPadでテンプレートを開き、生産記録の写真と気づき・改善提案を入力して投稿します。現場で記録を完結できるため、内容が後回しになりにくく、報告の質が安定します。
営業部は、事務所や外出先からその日のお客様の声や受注件数、売上などを日報で報告します。
これにより、現場で起きた出来事や顧客からの要望が、リアルタイムで社内全体に共有されるようになりました。営業が現場の進捗をすぐに確認でき、現場も営業の報告から顧客ニーズを把握できるようになったことで、部門間の情報格差がなくなりました。
テンプレート機能で報告を標準化
製造業では、報告の内容が部門によって異なり、情報が散らばりやすいという課題があります。MOTOMURAでは、日報アプリのテンプレート機能を活用し、各部門の業務に合わせた入力項目を設定しました。営業部門では「訪問先」「お客様の声」「自分の考え」、製造現場では「生産記録」「気づき・提案」「改善前後の写真」など、共通のフォーマットを使用。これにより報告内容のばらつきや漏れを防ぎ、どの部門の報告も同じ形式で閲覧・比較できるようになりました。
また、現場では既存の生産管理システムを活用しながら、その画面のスクリーンショットをアプリに添付する運用を採用。二重入力の手間を省きつつ、情報を「見る・使う」習慣を根付かせました。

結果として、報告内容が整い、他部門の取り組みを参考にできるようになり、日報アプリが改善事例の共有データベースとして機能しています。
コメント機能で部門を越えた対話が生まれる
日報アプリのコメント機能を通じて、報告が単なる提出で終わらず、社内コミュニケーションの起点となりました。営業の報告に現場が即座に反応し、管理者がフィードバックを送るなど、リアルタイムで意見交換が行われています。
投稿へのコメントやリアクションが可視化されることで、報告者は「自分の発信が届いている」という実感を得られます。その結果、日報投稿の継続率が向上し、社内全体で「書く」「読む」「反応する」の循環が生まれました。
こうした双方向のやり取りが増えたことで、現場の声が経営や開発部門にもリアルタイムで伝わる体制が整いました。情報が共有されるだけでなく、行動につながる仕組みが組織全体で定着しています。
日報アプリを導入することで、現場の意見が埋もれず、営業や管理職がすぐに反応できる。このスピード感こそが、製造業の改善サイクルを加速させています。
提出・改善状況を自動で可視化
同社では全社員に対し、「月に2件の改善報告を行う」ルールを設けています。以前は紙で提出された改善報告書を総務部が5拠点を回って回収し、社長が1枚ずつ目を通してポイントを付与。その後、担当者がExcelに入力してチームごとに集計していました。この運用は、報告の確認や集計に時間や手間がかかります。改善活動の状況をリアルタイムに把握できず、「頑張っているチームをタイムリーに評価できない」という課題もありました。
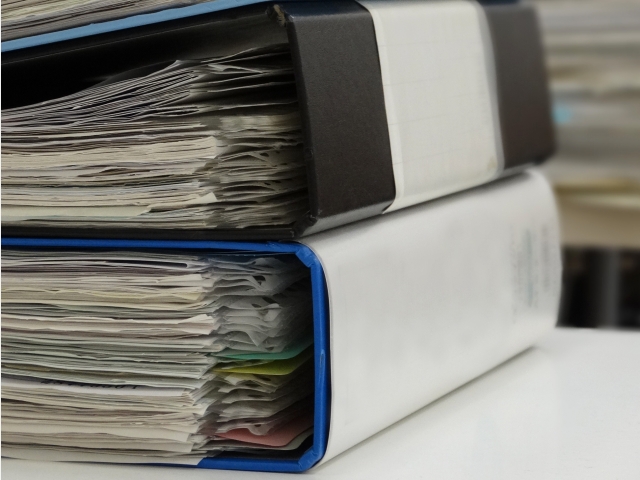
現在は、日報アプリの導入により、改善活動の投稿・承認・集計をすべてアプリ上で完結できるようになっています。
社員はアプリの投稿画面から改善報告を直接送信し、社長がアプリ上でそのままポイントを付与。承認状況や投稿数は自動的に集計され、リアルタイムで可視化されます。
さらに、アプリとGoogleスプレッドシートを連携し、Looker Studioでチーム別の提出率やポイントを自動集計。以前は手作業で行っていた集計作業が完全に自動化され、総務部門の負担が大幅に軽減されました。

この仕組みにより、社長や管理職がいつでも各チームの改善状況を確認できるようになり、「見える化」がモチベーションの向上にもつながっています。また、投稿履歴をもとに改善活動のテーマや傾向を分析できるようになり、全社的な改善方針の立案にも活用されています。
社内やお客様の声でアップデートを続ける日報アプリ
株式会社MOTOMURAの日報アプリは、導入して終わりではありません。現場や営業チーム、さらにはお客様の声をもとに、社内で継続的に改良を重ねています。
たとえば、製造現場からは「改善報告の写真をもっと簡単に添付したい」という声が上がりました。これを受けて、テンプレートに「改善前」「改善後」の写真欄を追加し、画像を並べて投稿できる仕様に変更しました。作業の様子が視覚的に共有できるようになり、他部署が参考にできる情報量も増えました。
こうした改良提案は、すべて日報アプリ内の「意見・要望」通じて投稿されます。社員が日常業務のなかで感じた改善アイデアをそのままアプリに残すことができ、開発チームがその内容を確認してアップデートに反映します。
この仕組みにより、社員の発言が実際の機能改善につながるという実感が広がりました。投稿件数は導入初期の月平均10件から、現在では月40件を超えるようになり、社内の開発スピードも向上しています。
また、営業を通じて得たお客様からのフィードバックもアプリ改善に活かされています。「もっと見やすく」「もっと早く」といった顧客の声が、アプリのユーザー体験(UX)向上へとつながっています。
このように、日報アプリそのものが「改善文化の中心」として機能し、現場・営業・開発が一体となって組織を進化させる循環が生まれています。
日報アプリは、単なる業務管理ツールではなく、社員の声を会社の力に変える“改善の仕組み”です。
まとめ:日報アプリが現場と組織をつなぐ改善の仕組みへ
株式会社MOTOMURAにおける日報アプリの導入は、単なる業務効率化にとどまりませんでした。現場の声が営業や管理層にリアルタイムで届くようになり、情報共有のスピードと質が大きく向上しました。
報告・提案・実行がアプリ上でひとつの流れとして循環することで、組織全体の行動が変化。社員一人ひとりが自分の意見を発信し、改善が日常的に生まれる文化が形成されています。
こうした変化を支えているのが、単なる報告ツールではなく「改善を生み出す仕組み」としての日報アプリです。現場が主体的に情報を共有し、経営が即座に反応できる環境は、製造業における競争力の源にもなっています。
製造業で現場改善を進めたい方は、実際の画面や機能、活用事例をまとめた日報アプリ導入資料(無料)をダウンロードしてご覧ください。導入までの流れや定着のポイントも詳しく解説しています。
また、無料トライアルでは、MOTOMURAのように「報告が改善につながる仕組み」を自社の現場で実際に体験できます。
現場の声を活かす日報アプリで、ムダな報告業務を減らしませんか?
紙やExcelでの管理をクラウド化し、現場と経営をリアルタイムにつなげる日報アプリです。チームの生産性を高める仕組みを、無料トライアル付きでご覧いただけます。
